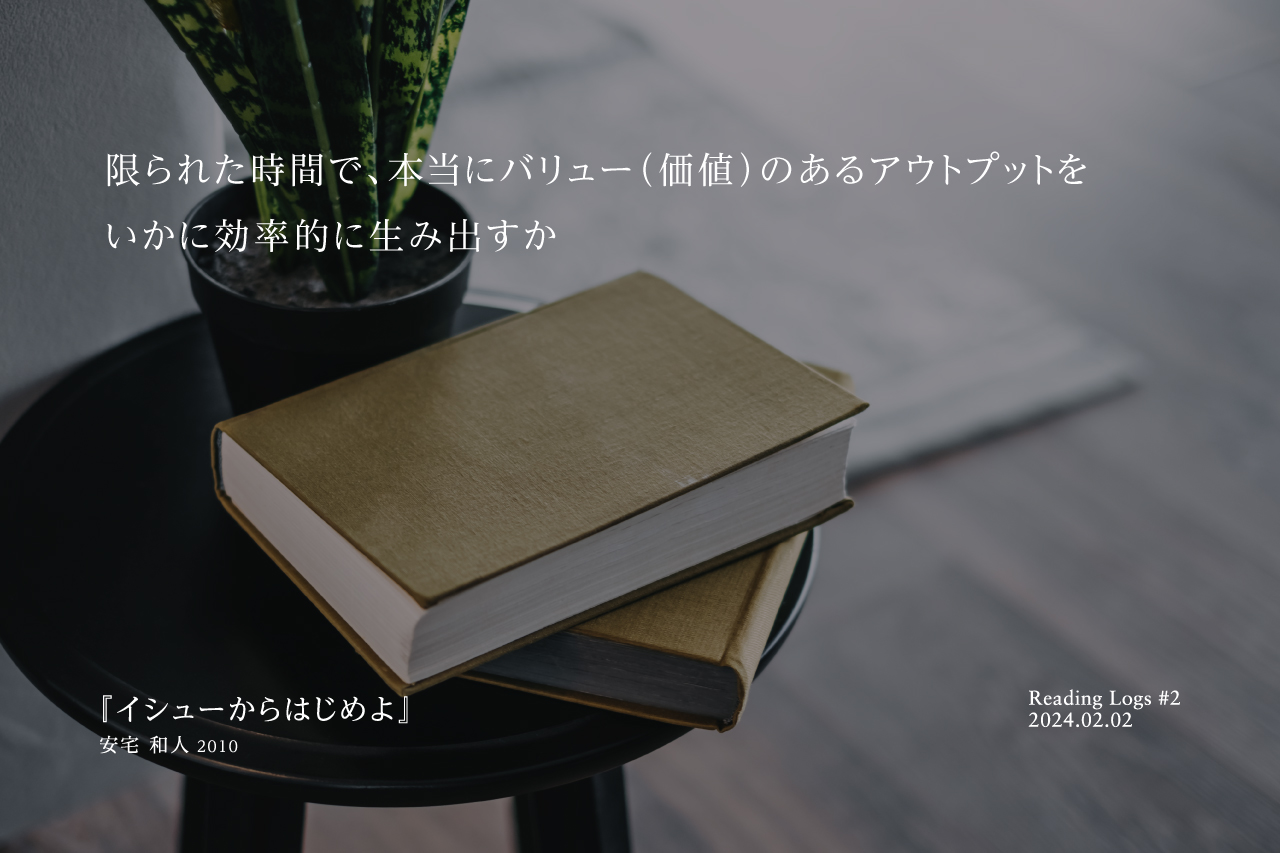限られた時間で、本当にバリュー(価値)のあるアウトプットをいかに効率的に生み出すか
『イシューからはじめよ』P.179 安宅和人(2010)
概要
本書『イシューからはじめよ〜知的生産の「シンプルな本質」〜』は慶応大学環境情報学部教授でZHD(現:LINEヤフー)のシニアストラテジストの安宅和人氏が執筆したもの。
10年以上外資系コンサルティング会社(マッキンゼー・アンド・カンパニー)に勤め、イェール大学脳神経科学の学位(Ph.D.)を持つ著者が、ビジネス・アカデミック領域に関わらず「本当に優れた知的生産には共通の手法がある」とし、その方法論を本書では紹介している。
販売開始から10年以上経った今も長く愛されるベストセラーである。
本書の目的・構成
このイシューが僕らの行う知的生産において、どんな役割を果たし、どのように役立つのか。イシューをどのように見分け、どう扱っていくのか、本書を通してそれを説明できればと思う。
『イシューからはじめよ』P.3 安宅和人(2010)
イシューとは何か、その見極め方、取り扱い方などを本書全体を通して説明している。そしてイシューから始めるアプローチを以下のように紹介し、それが本書の構成と連動している。
- イシュードリブン(第一章)「解く」前に「見極める」
- 今本当に答えを出すべき問題=「イシュー」を見極める
- 仮説ドリブン①(第二章)イシューを分解し、ストーリーラインを組み立てる
- イシューを解けるところまで小さく砕き、それに基づいてストーリーの流れを整理する
- 仮説ドリブン②(第三章)ストーリーを絵コンテにする
- ストーリーを検証するために必要なアウトプットのイメージを描き、分析を設計する
- アウトプットドリブン(第四章)実際の分析を進める
- ストーリーの骨格を踏まえつつ、段取りよく検証する
- メッセージドリブン(第五章)「伝えるもの」をまとめる
- 論拠と構造を磨きつつ、報告書や論文をまとめる
そもそも「知的生産」とはなにか
本書のサブタイトルにもある「知的生産」とは、そもそもなんだろうか。この点については特筆されてはいないが、その意味をおさらいしておこう。
知的生産は、文化人類学のパイオニアと呼ばれる梅棹忠夫氏が作った言葉で、著書『知的生産の技術』で以下のように紹介している。
知的生産というのは、頭をはたらかせて、なにかあたらしいことがら―情報―をひとに分かる方法で提出することなのだ、くらいにかんがえておけばよいだろう。
『知的生産の技術』梅棹 忠夫(1969)
企画書を作るにしろ、研究成果を発表するにしろ、頭を働かせて生産した情報であれば、知的生産であると言いうる。
この知的生産活動において、欠くことができない最も大事な根本の性質・要素=本質を『イシューからはじめよ』では紹介している。
話はズレたが、本書の内容に入っていこう。
イシューとは
本書で最も重要な概念が「イシュー」である。以下のように定義し、AとB両方の条件を満たすものがイシューとしている。
A)2つ以上の集団の間で決着のついていない問題
B)根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題
正直、イメージ付きにくいと思うだろう(少なくとも私はそう思った)。
以下の記事に分かりやすい具体例が提示されていたのでそれを紹介したい。
例えば、あなたの会社が売上の低迷に悩んでいるとしよう。リーダーであるあなたは以下のようなイシュー(=白黒つけるべき重要な問題)を設定したとする。
「どうしたら、売上を回復させることができるのか?」
このようなイシューを設定したあなたは、チームメンバーに「売上を回復させるアイデア」を指示することになるはずだ。
しかしぞくぞくと挙がってきたアイデアを前に、あなたは途方に暮れることになる。なぜなら、あなたの中に「どのアイデアを選択すべきか?」の基準がなく、優先順位がつけられないからだ。その結果「なんとなく良さそうなこのアイデア」という選び方となってしまい、その成果は不確かなものとなる。
しかし、もし仮に以下のようなイシュー(=白黒つけるべき重要な問題)を設定したらどうだろうか?
「売上が低迷している原因は何か?」
もしこのようなイシューを設定すれば、あなたはチームメンバーに「売上低迷の原因究明」を指示することになる。すると、やがて売上低迷の根本原因が明らかになるはずだ。そうすれば「売上低迷の根本原因を解決できるアイデアはどれか?」という基準でアイデアを選ぶことができるようになる。根本原因に対して対策を打つのだから、確かな成果が見込めるだろう。
このように「白黒つけるべき重要な問題の特定(=イシューの特定)」は、ビジネスの方向性に大きな影響を与え、時に命運すら左右する。よって、物事を考えたり意思決定を下す際には、拙速に「答え」を求めるのではなく「イシュー(=白黒つけるべき重要な問題)は何か?」を見極めることが必要だ。
イシュードリブンとは|イシューの例とイシュー思考の鍛え方 – Mission Driven Brand
上記記事では、「B)根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題」についてのみを前提としているが、ビジネス領域で考える場合は私もその方が使いやすいと思っている。
バリューのある仕事とは
本書では、バリュー(価値)のある仕事をイシュー度が高く、解の質が高い仕事であると表現している。
イシュー度とは「自分の置かれた局面でこの問題に答えを出す必要性の高さ」、解の質とは「そのイシューに対してどこまで明確に答えを出せているか」である。
多くの人は解の質がバリューを決めると考えるが、本当にバリューのある仕事をして、世の中に意味のあるインパクトを与えようとするなら、あるいは本当にお金を稼ごうとするなら、この「イシュー度」こそ大切だ、と説く。
ちなみに経営の父とも呼ばれるピーター・ドラッカーも、「何を問題にするか」ということに対して、以下のように表現している。
経営における最も重大な過ちは、間違った答えを出すことではなく、間違った問題に答えることだ
では「どうやってイシューを見極めるのか」、その手法が第一章に紹介されている。
イシュードリブン 「解く」前に「見極める」
良いイシューの条件として以下の3つを挙げている。
- 本質的な選択肢である
- 深い仮説がある
- 答えを出せる
他にも「老練で知恵のある人や、その課題領域に対して直接的な経験を持つ人などを相談相手として持つ」ことや、「仮説を立てる=スタンスを取ることの重要性」「イシュー特定のための情報収集方法」「イシュー特定の5つのアプローチ方法」なども本章では紹介している。
このイシューの見極め方から始まり、以下のように本書の内容は続いていく。
- 仮説ドリブン① イシューを分解し、ストーリーラインを組み立てる
- 仮説ドリブン② ストーリーを絵コンテにする
- アウトプットドリブン 実際の分析を進める
- メッセージドリブン 「伝えるもの」をまとめる
本書を読むことで、解くべき問題はなにか、その問題の構造化、必要な情報収集、伝えるための文章作成法などが一通りインプットできる。
所感
本書では、バリューのある仕事はどうやったらできるか?という議論に対し、絶対にやってはならないこととして「一心不乱に大量の仕事をする」ことを挙げている。この労働量によってバリューの高い仕事を行おうとするアプローチを「犬の道」と呼ぶ。
これが、私にはグサリと刺さった。
まさに今まで行ってきたアプローチは「犬の道」そのものだったからだ。依頼される仕事をいかに早く、大量に、質を担保しながら行っていくか、という仕事のやり方である。
私の仕事はデザインならびweb制作など受託業務がほとんどで、業界も特定領域ではなく、クライアントの課題も異なる。
依頼される仕事に対して「イシューはなにか」を深く考えることなく、「このパターンはこうだな」「こうすると及第点は出るだろう」という思考で仕事を「こなして」いたきらいがある。そのおかげでクライアントから「話が早いね」とか「短納期で助かる」と言われることもあった。それがある種アイデンティティに近いものであり、バリューの一つなのかもしれない。
が、その場合ある程度のアウトプットは出るが、大きなインパクトを与えられるような結果は出ない。実際、自慢できるような大きな結果は出ていない。
現在35歳。年を重ねるに連れ、多くの仕事をこなすことも体力的に厳しくなってきている。バリューのある仕事が出来なければ、淘汰されていくことは間違いないだろう。では、どうすればいいか?
それがこの本を通して、仕事の在り方、そして人生の在り方を再考する非常に良い機会になったと同時に、具体的にバリューのあるアウトプットを生産する手法を知ることができた。ぜひ次のプロジェクトで実践してみたい。
本書が長く愛されていることが強く実感できた。
仕事の進め方や、在り方に悩む人には、ぜひ手にとって頂きたい一冊である。
余談だが、大きなインパクトってなんだろう…と思った。雑に考えたのは、ビジネス領域においては「大きな利益を出しつつ、ビジョンに貢献し、人々のコミュニケーションを促すこと」とかそんな感じなのかもしれない。今度ゆっくり考えてみよう。
では。